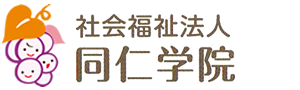<長期養護目標> 基本目標
「全ての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」児童憲章より
この児童福祉理念の実現のために、早期家庭復帰の実現と家庭的養育の実践に職員一同で取り組むことを基本目標とする。
①早期家庭復帰の実現については、家庭復帰または家庭機能の回復のために関係諸機関と連携しながら、児童の本来の家庭で生活できるように支援すること。さらに、社会的養護が長期化する児童に里親への委託を検討することなど。
②家庭的養育の実践については、家庭代替機能として、グループホームの実践と小舎制養育による生活環境の整備と健全な精神発達の保障のための養護をすることである。
<児童養護施設 中長期計画 2023年~2027年>
- 人材確保
近年人材確保が非常に困難になっている。職員の離職を防ぐことと、毎年安定的に職員を採用するための取り組みが必要となる。毎年4人~5人ほど退職者がでているため、平均で3人~4人くらいの退職者に抑え、採用に関しては毎年5人くらいの採用が出来ているので、平均6人くらいの採用ができるようにしたい。 - 人材育成 中級職員が初級職員に寮内でのOJTを行い、子どもへの良い影響等ポジティブな側面を中心に評価を行い、また、OJTを行う中級職員を主任が評価し育成するシステムを確立する。そのことにより職員のサポート体制をあつくし、職員のやりがいが感じられる養育環境を提供する。また、課題に応じた研修機会を提供し、キャリアアップを実感できるようにする。
- 経営施設整備 児童養護施設の建物は建築してから20年以上経過し、内装、外装の修繕が必要となっている。2022年度末でA棟の外壁塗装が終ったので、今後はB棟、センター、トポスの外壁塗装を順次行っていく。また、今後は子どもたちをグループホームで養育することが国の指針で決まっているので、職員数や設置場所を十分に考慮しながらグループホームを設置していく。
- 養育と専門性の向上 あいの実は、子どもとの愛着形成の為に縦割りの小舎制養育を実践し、住み込みと断続勤務を行ない、同じ職員が長く養育に関わる体制を極力整えてきた。人事において職員と子どもの寮異動を最小限にする努力もその一環である。住環境においては家庭的な雰囲気を大事にし、食事も全調理を行なっている。チーム養育を確立するため、職員間でのコミュニケーションを円滑にさせる。子どもの生活を第一に考え質の高い家庭的養育を追求するため、衣食住の養育内容について更なる充実を図る。
また、昨今高齢児の入所依頼が多い点、重篤な被虐待児や重い発達障害ほか、非常に大きな課題を抱えている児童が多い点などを踏まえると、養育環境の整備だけでなく、職員の質の向上も必須である。研修の充実や普段のOJTにより知識を高め、子どもへの対応力を学び、施設の高機能化を目指す。 - 権利擁護 「権利」とは何かを職員も子ども学んでいく文化を築き、人間同士お互いを尊重し合えるような雰囲気を育てていく。子ども全てが安全で安心な暮らしができる環境を目指す。これまで行なってきた児童養護施設における人権擁護のためのチェックリストや、権利擁護のための事例検討を継続するとともに、啓発活動や権利擁護に関わる研修や取り組みを計画・実施していく。
支援目標
- 安心して暮らせる寮であること
1)基本的な生活習慣を身につける
2)あいさつを交わし優しい言葉遣いをする - 住環境の整備
1)室内外ともに気持ちのいい生活環境作りをする - 良い食生活の習慣
1)体に必要な栄養やバランスだけでなく、食生活全般についての知識をもつ - 学習する習慣
1)基本的な学力をつける
2)時間を決め勉強する - 児童と家族の支援
1)児童とその家族の抱える問題に耳を傾ける
2)児童自立支援計画に沿って、関係諸機関との連携の上、早期家庭復帰を図る
3)被虐待児を含む児童とその家族の機能回復のために、治療的養育を行う - 職員の専門性の向上
1)施設内外で行われる諸研修に積極的に参加する等、自己研鑽に努める